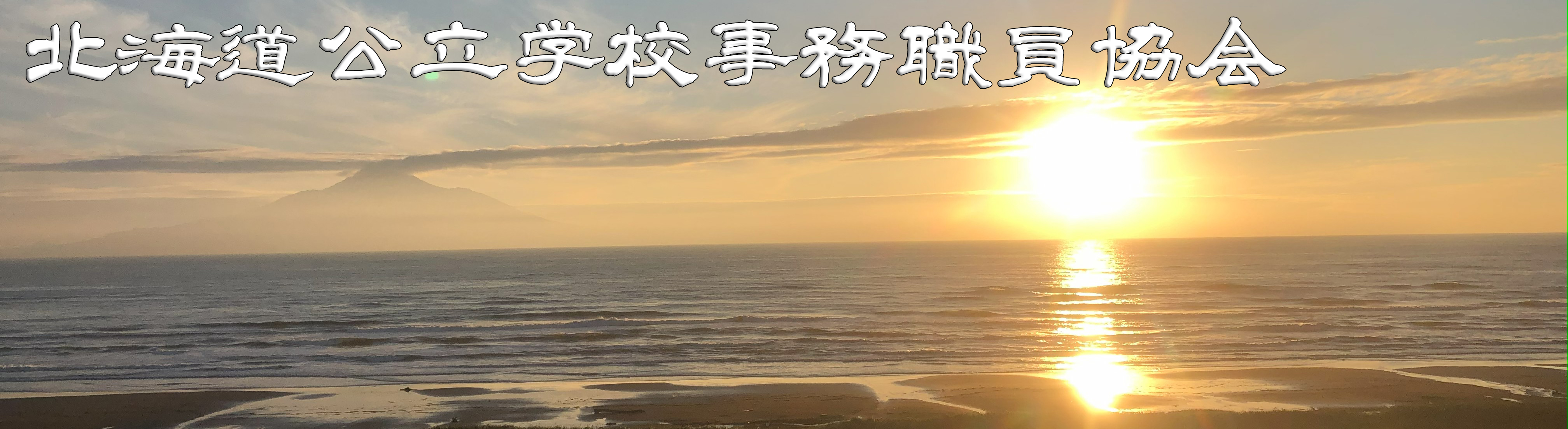昭和43年度
43. 8.12 第21回全道研究大会並びに総会開催。(札幌市)
43. 9. 9 第1回評議員会開催。
43. 9.24 道教育長との座談会打合会開催。
43.10. 4 文部省主催事務職員研修会開催される。
43.10.31 岡村教育長と「学校事務の諸問題」について座談会を開催。
43.11.19 授業料収納対策について道教育庁と協議。(以後5回開催)
43.11.28 第2回評議員会開催。
43.12.10 会報第15号発行。
43.12.25 事務長管理職手当支給について、道人事委員会並びに道教育長に事情説明書を提出。
44. 2. 3 教育庁総務課長と座談会開催。
44. 2.20 教育庁財務課長と座談会開催。
44. 2.24 第3回評議員会開催。
44. 3.15 会誌第11号発行。
44. 3.25 授業料収納方法について、教育庁説明会が、札幌南高校で開催される。
44. 5.22 第4回評議員会開催。
44. 6.10 会報第16号発行。
44. 7. 4 授業料収納方法改正後の追跡調査を行う。
44. 7.15 第5回評議員会開催。
44. 7.29 第22回全国研究大会並びに総会開催される。(仙台市)
授業料収納方法改正
前年度からの懸案だった授業料収納方法については、道教育庁と数回にわたって協議を重ねた結果、従来の証紙方式から、現金収納によるパートタイマーの雇用に改められ、収納成績の向上が期待された。
授業料収納方法改正後の実態調査実施
授業料現金収納に改正されたのでその実態を調査した、この調査は全道的に非常に関心が強く、回収率83%に達した。調査結果は次のとおり。
- 事務量が増加し、複雑化した。
- 従来の証紙制度より取扱いの誤りが減少した。
- 地域によっては協力員の採用に困難を感じた。
- 大規模校ほど協力員の人員不足を訴えている。
- 協力員は未経験者が多く、女性が圧倒的に多い。
- 収納指定日を多くするほど(10日間が最もよい)収納率が向上している。
教育長との座談会
関係機関及び諸団体との意志の疎通と、より連帯意識を深めると共に学校事務諸問題解決のための一方策として、教育長との意見交換の場をもち、基本的問題の検討と、学校事務の諸問題について話し合い、続いて関係課長を中心とした附随問題についての座談会を数回にわたり開催し、協会が意図している数々の問題点を解明し、遂次これが行政措置され具現化された。
座談会でとりあげられた問題点は次のとおり。
- 本庁、局、学校間の人事交流の一元化。
- 学校事務職制の確立。
- 学校行政職員の担当窓口の設置。
- 事務職員の処遇改善。
- 事務職員の定数増。
- 授業料収納事務の改善。
- 学校事務標準化についての相互理解。
- 事務職員の研修(海外視察を含む)の強化促進。
昭和44年度
44. 8. 8 第22回全道研究大会並びに総会開催。(札幌市)
44. 9.17 第1回評議員会。
44. 9.19 学校事務資料編集委員会設置。(年度内5回開催)
44. 9.29 処務規程起草委員会設置。(年度内5回開催)
44.10.10 会報第17号発行。
44.10.20 教育庁に道立学校事務改善委員会設置される。
44.11.19 文部省主催事務職員研修会開催される。
44.11.24 第1回道立学校事務改善委員会幹事会開催される。
45. 1.10 第2回評議員会開催。
45. 1.12 第1回道立学校事務改善委員会開催される。
45. 1.23 教育庁財務課に団体会計事務処理要領作成委員会設置される。
45. 2.13 道教育庁に道立学校教務、事務部の学校長決裁事項の調査書を提出し、事務長専決事項の審議を行う。
45. 2.20 事務長管理職手当に関する人事委員会規則改正について道人事委員会事務局長と懇談。
45. 3.15 会誌第12号発行。
45. 5.26 第3回評議員会開催。
45. 6.15 会報第18号発行。
45. 7. 2 道立学校事務長管理職手当支給決定(45.4.1適用)
45. 7.15 第4回評議員会開催。
45. 7.28 第23回全国研究大会並びに総会開催される。(鹿児島市)次期開催地、北海道に決定。
道立学校事務改善委員会
急激な社会情勢の変化は、教育行政面に与える影響が大きく、学校における不祥事故の発生もあり、これに対応するため教育庁に本委員会が設置された。
道立学校事務改善委員会設置要綱(抜萃)昭和44.10.20
第1条 教育庁に、道立学校事務改善委員会を置く。
第2条 委員会は、道立学校における事務の適正かつ公正な執行をはかるため、学校事務に関する具体的な改善計画を策定し、その結果を教育長に報告する。
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2、委員長は、管理部長をもって充てる。
3、委員は、管理部の総務課長、財務課長、教職員課長、学校管理課長及び教育長が指定する教育局長1名並びに教育長が指定する道立学校の校長5名及び事務長1名をもって充てる。
第5条委員会の事務を処理するため、管理部総務課に事務局を置く。
1、事務局に幹事を置く。
2、幹事は教育長が指定する職員をもってあてる。
委員会、幹事会では、道立学校処理規定の制定、団体会計の改善の2点を具体化することに決定された。
処務規程起草委員会
学校機構の中で責任体制を明確にし、学校事務の標準化をはかるためこの委員会を設置、道立学校事務改善委員会と綿密な連絡をとりながら次の基本方針、内容により原案を作成した。
- 処務規程制定に伴う管理規則との関係について。
管理規則にふれない程度のものを原則とし問題点を検討する。 - 処務規程の内容について
総則、校務分掌、職務権限、文書の取扱い、公印、服務、宿日直、夜警等 - 進行計画
12月中旬までに規程本文、原案を作成する
尚起草委員会で作成した原案は、道立学校事務改善委員会の重点協議事項として審議された。(註、数年を経た今日未だ制定をみていないので今後早期制度化の折衝を強めなければならない。)
学校事務資料編集委員会
財務会計事務処理の完壁を期し、事務職員の資質向上に資するため、本委員会を設置して、「物品種別表と国庫補助台帳物品名との対応表」の作成にとりくんだ。
内容は、第22回全道大会で、旭川支部土曜会が発表した理振、産振、定振、外の対応表に順次、更に農業科、工業科、水産科について対応表を作成するもので、2月完成をめどに作業をすすめた。
団体会計事務処理要領作成委員会
団体会計事務の改善については、道立学校事務改善委員会の重点協議事項でもあることから、財務課所管でこの委員会が発足した。
事務長管理職手当支給決定される
北海道人事委員会規則7-346(抜萃)
管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
昭和45年7月2日
高等学校
校長 4種
教頭、定時制主事、事務長(人事委員会の定めるものに限る。)
5種
盲学校、ろう学校、養護学校
校長 4種
教頭、事務長(人事委員会の定めるものに限る。)5種
附則 この規則は公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
懸案事項であった事務長管理職手当は、人事委員会規則の改正により支給決定された。人事委員会の定めるものに該当する学校は全道で72校であった。
昭和45年度
45. 8. 7 第23回全道研究大会並びに総会開催。(帯広市)
45. 9. 4 学校事務組織編集委員会を設置。(年度内6回開催)
45. 9. 7 事務手引編集委員会設置。(年度内6回開催)
45. 9.22 第1回評議員会開催。
45.10.10 会報第19号発行。
45.11. 5 第24回全国研究大会(札幌大会)運営審議委員会並びに準備委員会を設置、全国大会の準備開始。
45.11.20 文部省主催事務職員研修会開催される。
45.11.26 全国研究大会第1回準備委員会開催。
45.12. 2 全国研究大会会場決定(札幌市民会館外)
46. 1.12 第2回評議員会開催。
46. 1.30 道立教育研究所と学校事務改善、学校事務研修に関する調査の打合せを行う。
46. 3. 3 道立学校団体関係事務処理要領(準則)が出される。
46. 3.12 全国研究大会について、文部省並びに全国本部と打合せを行う。(東京)
46. 3.18 全国大会募金活動開始。
46. 3.25 全国大会要項作成、案内状発送。
46. 4.27 第3回評議員会開催。
46. 5.25 国庫補助物品対応表編集作業を開始。
46. 7.16 道立教育研究所主催「学校事務改善」について座談会開催される。
46. 7.26 第4回評議員会開催。
46. 8. 3 第24回全国研究大会並びに総会開催。(札幌市民会館外3会場)
学校事務手引編集委員会
設置目的
日常の事務運営に当り、与えられた仕事の処理に対し平均した力と理想なる環境によって事務処理が迅速に完結にされていくことが、最大の条件と考えられる。
なかでも、日常事務の能率化、新規採用者の早期育成、部内分掌交替時及び学校種別替勤務時の事務引継ぎの徹底化、或いは日頃の会員の研究事例の活用等、これらを目的に事務実践上の実務資料の発刊が、会員の多くから要望が出されていた。協会として事業計画の重要項目として専門委員会を設置し、協会の恒久事業としてとりくむことにした。
編集の力点
- 事務分類表により整理区分を明確にする。
- 法規編は日常利用度の高いものの条例、規則、通達等を入れる。
- 実務資料編は、
事務処理系統表を作成する。
事務処理要領を作成する。
様式類集(記載例)を作成する。
その他参考図表を多く取り入れる。 - 会員並びに協会の事業等で過去に研究された事例をとり入れる。
昭和45年9月29日第1回事務手引編集委員会を開催して、編集作業を開始する。
学校事務組織研究委員会
設置目的
学校教育の目的遂行のための学校事務組織、機構及び職務内容の分析により学校事務の理想像を追求して、近代化に資するために本委員会を設置した。
研究目標
学校経営の中において、教育活動が円滑に且つ充分行われ、教育水準の向上を期するため、学校事務機構、組織及び業務内容のあるべき姿について研究し、その理想像を追求する。
研究内容
- 学校事務全般の分析検討と職能分析
イ、教育職員が行っている事務、事務職員が行っている事務の洗い出しと体系づけ。
ロ、教育職と行政職間の本来あるべき姿への事務配分。 - 学校に於ける事務の整理
イ、現在学校の行っている事務のうち直ちに本庁、局に移行すべきもの、出来得る
ものの検討。
ロ、工夫すれば他に移行出来るものの検討。
ハ、現在学校が行っている事務以外の学校独自の事務の有無検討。 - 事務処理の方法
イ、事務処理改善具体案の作成。
ロ、事務処理機構と職員組織の検討。
道立学校管理規則改正
道立学校管理規則の一部改正(昭和46.4.21)(校長の職務の代行等、昭和46.5.1から施行)により事務長の代決規定が明文化され、学校組織の中での職能分野における責任と権限が明確になった。
永年の懸案事項の一角が解決され、理想とする学校機構実現への足がかりとなる。
団体会計事務処理要領
前年度道立学校事務改善委員会の重点事項としてとりあげられていた団体会計の改善は、財務課が中心になって検討されてきたが「団体会計事務処理要領」(準則)として出された。
第24回全国大会(札幌)
第23回鹿児島大会終了後、第24回北海道大会の準備に入った。
全国大会を開催することは、経費、労力或は準備に相当な覚悟を要するものだが、全国会員の要望もあり、地元北海道会員が多数参加できることでもあり、我々にとっても輪番制をとっている全国協会の意に添うべく、全道会員の理解と協力のもとに準備をすすめた。
まず、運営審議会、準備委員会を構成し、具体的な準備に入ったが、会場の検討、予算の確保、要項の編集、受入態勢、大会当日の運営等の勇は予想以上のものがあった。又その中で北海道大会らしさをどう表すかという問題もあった。
参加者2611名、研究発表者25名とかつてない大規模な大会になったが、関係機関の協力と太田音一会長のもと会員各位の努力が実を結び盛会裡に終了することができた。
昭和46年度
46. 9.10 総会代替評議員会を開催。(札幌市)
46. 9.12 文部省主催海外教育事情視察のため、札幌南高校3浦藤吉事務長が派遣される。(10月13日帰国)
46. 9.16 第24回全国研究大会準備委員会を解散する。
46.10.13 第2回評議員会を開催。
46.10.20 文部省主催事務職員研修会開催される。
46.10.31 道費派遣事務職員道外視察出発。(3班編成)
46.11.11 会報第21号発行。
47. 1.12 第3回評議員会開催。
47. 3.31 道立学校事務実務提要発刊。
追録1、2、3号発行。
47. 4.25 第4回評議員会開催。
47. 6.17 室蘭支部と苫小牧支部を統合し、胆振、日高支部に変更。
47. 7.12 道人事委員会に対し、事務職員の処遇改善について陳情。
47. 7.12 第5回評議員会開催。
47. 7.25 第25回全国研究大会並びに総会開催。(松山市)
総会代替評議員会
第24回全国大会を北海道で開催したため、全道研究大会をとりやめ総会は評議員をもってこれに替えた。
学校事務手引完成
前年度から継続してとりくんできた学校事務手引は、事務手引編集委員会設置から今日まで、膨大な資料、原稿の執筆にとりくみ、委員会の会議も回を重ね、種々の問題点にぶつかりながら、これを編集委員一丸となって克服し、遂に昭和47年3月31日「道立学校事務実務提要」の発刊をみた。ここに本協会の大事業の一つが完成し、同時に追録発行という恒久事業を開始することになった。
今後は追録事業がとだえることなく、全会員の理解と研究協力により改善を加え、理想的な「手引書」となることを期待する。(本誌別稿藤田編集委員長の投稿を参照願いたい。)
事務組織の研究
前年度に引続き事務組織研究委員会を開催、研究目標にもとづき10回の委員会を開催、委員各位のひたむきな追求により「転換期に来た学校事務の理想像を指向する改革案」として研究がまとまった。
本委員会の研究の経過の中では、現時点において定数や法令規則、予算の関係等問題の解決、その他隘路等を考えるとき、未来に向っての理想像を掘り下げることは容易ではなく、理想像をどの辺にとらえるかによって研究結果も変ることでもあり、その辺が研究委員の苦労されたところのようである。
なお、この改革案は、全国大会で発表した。
事務識員の海外視察
文部省主催海外教育事情視察団に、事務職員の参加がようやく認められた。札幌南高校3浦藤吉事務長が派遣された。帰国後は視察記を会誌に投稿し、全道研究大会はもとより全国研究大会でも海外視察講演を行った。
昭和47年度
47. 8.10 第25回全道研究大会並びに総会開催。(留辺蘂町)
47. 9. 9 小樽、後志支部を統合し後志支部に変更。
47. 9.20 第1回評議員会開催。
47. 9.30 帯広柏葉高校山越近次事務長「教育功労者」として文部大臣表彰決定。
47.10.13 事務手引追録編集委員会を開催。(年度内5回開催)
47.10.16 文部省主催事務職員研修会開催される。
47.10.20 道立学校道内外研修視察者、道内10名、道外10名決定。
47.10.27 財務会計事務チェックリスト作成について財務課と協議。
47.11.10 会報第23号発行。
47.11.15 事務手引追録第4号発行。
47.12. 4 山本教育長と懇談会を開催。
48. 1.12 第2回評議員会開催。
48. 1.17 道出納局主催部局地方部局会計職員座談会開催され、3浦副
会長外6名出席。
48. 3.20 道人事委員会に事務職員処遇改善について陳情。
48. 3.30 会誌第15号発行。
48. 3.31 中村正一会長退職。
48. 4.23 第3回評議員会開催。
中村会長退職に伴う後任として、3浦藤吉副会長が会長代行として会務をとることに決定。
48. 6.30 会報第24号発行。
48. 7.10 第4回評議員会開催。
48. 7.31 第26回全国研究大会並びに総会開催される(金沢市)]
財務会計チェックリスト
日常の会計事務の整理、点検を目標に、研究部が担当して、財務会計チェックリストを作成し各学校に配付する。
事務手引アンケート集計
本協会が発刊した「道立学校事務実務提要」の利用状況は、非常に気になることの一つでもあり、今後の追録発行事業にも関係があるので、アンケートをとり利用状況の集約を行った。
結果は、
常に利用する…事務長53%・事務職員40%
必要に応じ利用する…事務長40%.事務職員54%
たまたま利用する…事務長7%・事務職員6%
又、校長.教頭・教諭でも何等かのかたちで利用している方が13%あった。
アンケートは右の項目の外に「事務実務提要」と他の法全集との利用関係の調査も実施した。アンケート集約の結果により非常に利用されていることがわかり、今後の追録事業を進める上に於て意を強くした。
事務組織アンケート集約
「転換期にきた学校事務の理想像を指向する改革案」に基き、会員各位の意見をアンケートにより集約した。
結果は、
- 事務処理機構と定数について改善をのぞむ。
- 金銭出納の集中化をのぞむ。
- 事務処理の一元化について改善をのぞむ。
- 電子計算機の活用をのぞむ。
- 文書、資料の集中管理データーセンターの設置をのぞむ。
等の意見が強く出されている。
中村正一会長退職
永い間協会の役員を歴任された会長中村正一氏が、3月31日付で退職されたため、3浦藤吉副会長が代行として会長の職務をとることになる。
昭和48年度
48. 8.10 第26回全道研究大会並びに総会開催。(小樽市)
48. 9.19 事務手引追録編集委員会開催。(年度内6回開催)
48. 9.26 文部省主催海外教育事情視察のため小樽潮陵高校坂井忠夫事務長が派遣される。(10.27帰国)
48.10. 2 第1回評議員会開催。
48.10. 4 道立学校道外視察者10名決定。
48.10.20 会報第25号発行。
48.10.25 文部省主催事務職員研修会開催される。
48.10.26 事務手引追録第5号発行。
48.11. 5 道立学校道内視察者10名決定。
48.11. 8 物品種別表改正検討協議会開催。
48.12.10 物品種別表改正について出納長に対し要望書を提出。
48.12.27 道人事委員会、道教育長に対し、事務職員処遇改善等について陳情。
49. 1.10 第2回評議員会開催。
49. 2.20 北海道教育長期総合計画の策定について道教育長に答申。
49. 3.15 会誌第16号発行。
49. 4.15 第3回評議員会開催。
49. 4.30 事務手引追録第6号発行。
49. 7.10 第4回評議員会開催。
49. 7.30 第27回全国研究大会並びに総会開催される。(山口県)
財務規則・物品種別表改正について
北海道出納局が、昭和49年4月1日から改正予定で「北海道財務規則」の改正、これに伴う「北海道物品種別表」の改正試案を出した。更に道教育庁ではこれに関連する「道立学校物品事務取扱い要項」の改正を要することとなった。
財務課では、これを機会に道立学校の意見を反映した改正をさせるべく、本協会に諮問があり、研究部が担当して、出納局に要望書を提出した。
北海道教育長期総合計画の策定について(回答)
昭和49年2月14日付「北海道教育長期総合計画」の策定について道教育長より諮問があり次の5項目について回答した。
- 道立学校の事務処理規程の早期実施
道立学校文書管理規程
道立学校公印管理規程
道立学校事務専決規程 - 学校経営近代化のため学校事務の合理化能率化を進める。
行政事務の集中管理方式の実施(出納事務所を14支庁ごとに設置) - 学校事務職員の資質の向上をはかる。
研究体制の充実を計る
事務職員の任用制度の改善
事務職員の処遇の改善
人事交流の広域化(学校、教育局、教育庁、道機関) - 事務職員定数の充実
事務職員定数配置の均等化(特に小規模校) - 教育予算の充実
学校予算は道費と団体会計との関連で執行されているのが現状であるが、学校管理運営は、団体の後援なくして執行できるよう、道教育費予算を増額されたい。
(転換期にきた学校事務の理想像を指向する改革案を資料として添付)
事務職員海外視察
前年度実現をみなかった事務職員の海外教育事情視察は、本年度1名派遣が認められ、小樽潮陵高校坂井忠夫事務長が参加する。
昭和49年度
49. 8. 9 第27回全道研究大会並びに総会開催。(美唄市)
49. 9. 4 道立学校管理規則一部改正原案が教育庁から提示される。
49. 9.10 人確法に関連して処遇改善について道教育庁、人事委員会に陳情。
49. 9.16 会報第26号発行。
49. 9.19 第1回評議員会開催。
49. 9.25 文部省主催海外教育事情視察団に函館西高校草彅弘一事務長が派遣される。(10月25日帰国)
49. 9.27 事務手引追録編集委員会開催。(年度内9回開催)
49.11.10 会報第27号発行。
49.11.16 道立学校管理規則一部改正にかかわる事務長代決権について教職員課長に陳情。(年度内4回)
49.11.13 文部省主催事務職員研修会開催される。
49.12.21 人確法に関する事務職員処遇改善運動についての賛同者集約方を支部長に依頼。
50. 1.11 第2回評議員会開催。
50. 1.20 事務職員の処遇改善運動(人確法関連)について、北教組、高教組と懇談。
50. 3. 3 支部研究担当付会議を開催する。
50. 3.15 会誌第17号発行。
事務手引追録第8号を発行。
50. 4.22 第3回評議員会開催。
50. 6.13 道教育長に対し当面する諸問題について陳情。
50. 7.10 第4回評議員会開催。
50. 7.30 第28回全国研究大会並びに総会開催。(堺市)
道立学校管理規則改正
学校教育法の一部を改正する法律の成立に伴った、道の関係条例、規則の整備に関連して事務長の職務権限の問題として、道立学校管理規則4条の2について(従来の事務長代決権条文削除)、道教育長関係機関と精力的に折衝の結果「教頭及び事務長の事務代決について」の教育長通達が出された。
事務職員の処遇改善運動
事務職員の処遇改善については、本協会重点事業の一つであり、従来から継続して強力な陳情要請を行ってきたところであり、徐々にではあるが改善の方向をたどり今日に至っている。
人材確保法成立に関連しての処遇改善については、北海道段階はもとより全国協会組織をもって処遇改善特別委員を設置して、強力に推進する計画を進めたが、途中で種々の障害が生じ、全国的意志統一ができなく、特別計画による運動は中止となった。
本協会の年度計画に基づく処遇改善は引続き強力に推進した。
事務職員の海外視察
事務職員の海外教育事情視察は、関係機関のご努力により長期1名派遣が決定し、函館西高校草彅弘一事務長が参加する。
支部研究担当者会議の開催
支部研究活動の推進と、本部と支部の連携を一層緊密にするため、本年より支部研究担当者会議を開催することにした。
昭和50年度
50. 8.10 第28回全道研究大会並びに総会開催。(旭川市)
50. 9.20 事務手引追録第9号発行。
50. 9.26 第1回評議員会開催。
50.10.11 事務手引追録編集委員会開催。(年度内6回)
50.10.15 文部省主催事務職員研修会開催される。
50.10.22 公立学校事務長の職制及び職務の確立について文部大臣に要請。
50.11.16 授業料徴収方法改善検討委員会を設置し、第1回委員会を開催する。(年度内7回開催)
50.11.20 会報第29号発行。
50.12.12 公立学校事務長の職制及び職務の確立について文部大臣及び関係議員に陳情書提出。
50.12.25 事務職員の処遇改善について道人事委員会並びに道教育長に陳情。
51. 1.12 第2回評議員会開催。
51. 2. 6 本協会理事総務部長小松重夫氏ご逝去。
51. 2.10 事務手引追録第10号発行。
51. 3.20 会誌第18号発行。
51. 5.13 第3回評議員会開催。
51. 6.10 30周年記念誌編集委員会を設置。
51. 6.30 会報第30号発行。
51. 7. 7 第4回評議員会開催。
51. 7.28 第28回全国研究大会並びに総会開催。(横浜市)
学校教育法施行規則改正
事務長法制化について永年全国協会を中心に陳情、請願運動を続けてきたが、実現をみず今日に至っている。今回の学校教育法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、事務職員の組織及び事務長の職制と職務を省令上明確に規定されたものである。協会としては当初より法制化を請願陳情しており、今回の省令化を段階的獲得であるとの見解にたって、今後所期の目的である法制化に向けて、精力的に運動を継続していかなければならない。
30周年記念誌編集委員会
52年度に控えた、30周年記念事業の一環として、記念誌編集委員会を発足させ、52年度発行を目途に編集作業に入った。
市町村分科会の新設
第29回大会に向けて、新しい試みとして、市町村部会を設け、協会事業との関連が稀薄となりがちな、市町村立高校に、自由な発言の場を設けることにした。今後の研究活動の基盤となることを期待したい。
授業料徴収方法改善検討委員会設置
第27・28回全道研究大会において授業料の徴収方法の改善に関する研究発表が続いて多く出され、この間題に対する会員の関心が非常に高まってきたことと、併せて研究成果の活用の観点から、特別委員会として、授業料徴収方法改善検討委員会を設置し、研究を進めた。
検討委員会に付託した検討事項
- 授業料徴収方法の検討
① 現行徴収方法の問題点
② 団体会計の取扱い - 授業料徴収方法の改善について
① 改善を必要とする事項
③ 改善の方法 - 意見集約
① 父兄及び関係者の意見
② 道立高校のアンケート調査
③ 函館大会で報告(中間報告) - まとめ
① 改善案(試案)作成
② 改善案実施の可否について意向調査
昭和51年度
51. 8. 9 第29回全道研究大会並びに総会開催。(函館市)
51. 8.18 授業料徴収方法改善検討委員会開催。
51. 9.17 30周年記念誌編集委員会開催。
51. 9.20 授業料徴収方法改善に関する要望書を教育長に提出。
51. 9.27 第1回評議員会開催。総務課長と懇談会開催。
51.10. 7 第1回事務手引編集委員会開催。
51.10.18 総務課長及び学校施設課長と懇談。
51.11. 9 北海道公立学校事務長会設立総会開催される。
51.11.16 支部研究担当者会議開催。
51.12.27 事務職員処遇改善について道人事委員会、道教育庁に陳情。
52. 1.14 第2回評議員会開催。
52. 2.16 第1回定員間題調査委員会開催。
52. 2.19 授業料徴収方法改善検討委員会開催。
52. 4.15 事務手引追録第12号発行。
52. 4.26 第3回評議員会開催。
52. 6. 7 支部研究担当者会議開催。
52. 7. 8 第4回評議員会開催。
52. 7.28 第30回全国研究大会並びに総会開催される。(岐阜市)
30周年記念事業について
創立30周年を迎えるにあたり、函館大会で決定した次の記念事業について準備をすすめる。
- 記念誌の発行
- 記念講演
- 記念式典、功労者の表彰
- 祝賀会の開催
記念誌編集委員会
記念誌の編集計画に基づき、業務分担を行い、資料の蒐集、原稿の依頼、座談会の開催と原稿の整理、協会30年の歩み原稿作成等、積極的に完成をめざしてとりくんだ。
授業料徴収方法改善検討委員会
前年度函館大会に於て中間報告をした。以後残された問題点として、次の3項目を研究し、第30回滝川大会までに成案を得て、改善案(試案)を報告することになる。
- 条例規則関係様式
- 電算処理要領及び様式
- アンケートの集約
なお、協会は、道立学校授業料等徴収事務改善に関する要望書を道教育長に提出し検討を要請した。
定員問題調査委員会
設置目的
学校教育の正常な維持発展を期すべく、学校管理運営上事務の現状を見るとき、質・量の両面から思考して、現行定数は満足すべきものではない。定数についての抜本的な改正のため、数年前より多くの会員から改善について提起がなされ今日に至っている。
授業料徴収方法の改善についても、関連することは必至であり、授業料協力員の措置とも考え合せ研究すべき時期に来ていると考え、本委員会を設置した。
委員会に付託した事項
- 授業料電算化実施に関連して定員問題並びに授業料協力員の存廃等についての調査研究。
- 小規模校(定員2名)における定員についての調査研究。
- 特殊学校における定員についての調査研究。
- その他実業高校並びに普通高校における定員問題について調査研究。
昭和52年度
52. 8. 9 創立30周年記念第30回全道研究大会並びに総会開催。(滝川市)
52. 9.20 第1回評議員会開催。
52. 9.27 第1回定数問題調査委員会開催。(年度内7回開催)
52. 9.27 創立30周年記念事業として北海道交通遺児の会へ寄付。
52.10. 1 事務手引追録第13号発行。
52.10. 7 事務手引追録編集委員会。(年度内6回開催)
52.10.24 道人事委員会、道教委に対し、事務職員処遇改善等について陳情。
52.10.24 会報第33号発行。
52.10.27 文部省主催公立学校事務職員研修会開催。
52.11. 8 第1回各支部研究担当者会議開催。
52.12.15 会報号外発行。
53. 1.12 第2回評議員会開催。
53. 2. 9 学校備品基準調査打合せ会議開催。
53. 3.13 道教委に対し、授業料等徴収事務改善等について陳情。
53. 4.10 事務手引追録第14号発行。
53. 4.25 会誌第20号発行。
53. 5.11 第3回評議員会開催。
53. 6. 9 第2回各支部研究担当者会議開催。
53. 6.25 会報第34号発行。
53. 7.10 第3回評議員会開催。
53. 7.26 第31回全国研究大会並びに総会開催。(青森市)
定数問題調査委員会
かねてから永年にわたる会員の願望でありました事務職員の定数問題の要望活動に関する資を得る目的で、昨年度より精力的に研究を継続しましたが、この研究成果について釧路大会で報告し、委員会の使命を終えました。
委員会に付託した事項
- 授業料等徴収事務電算化実施に関連して定数問題並びに授業料徴収協力員の存廃等についての調査研究
- 小規模校(定員2名)における定数についての調査研究
- 特殊学校における定数についての調査研究
- その他実業高校並びに普通高校における定数問題についての調査研究
事務職員処遇改善等について陳情
事務職員の処遇改善については、財源事情が好転しない現状にあって、北海道教育委員会及び人事委員会に対する改善要求も特記すべき成果は得られませんでした。
規程外帳票の共同印刷作業
研究部担当者の献身的な苦労と努力で、全員諸氏のご期待と活用に応ずべく、共同印刷作業事業が行なわれた。
「道立学校帳票様式類一覧表」と「特殊ファイル(ネタ用紙収納用)」の作成をしました。
会誌20号
創立30周年記念誌発行のため会誌19号を欠号として、昭和52年度は会誌20号を発行しました。
道立学校備品基準表
北海道教育委員会から依頼をうけ、今後の教育費予算要求資料として道立学校備品基準表の作成をしました。